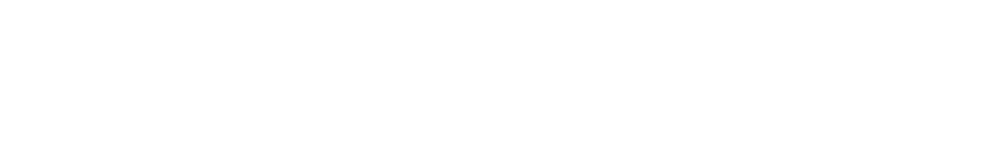猛暑の夏を乗り切ったと思ったら、体がだるい、やる気が出ない、頭痛やめまいが続く…。そんな症状を感じていませんか?最近では、このような状態を「秋バテ」と呼ぶことがあります。夏バテが完全に回復しないまま季節の変わり目を迎え、さらに朝晩の気温差や気圧の変化によって自律神経が乱れやすくなるのが特徴です。
当院では頭痛やめまいの診療を行っており、季節の変化に伴う体調不良でお困りの方からも多くご相談をいただいています。
秋バテの原因
秋バテの主な原因は、自律神経の乱れにあります。夏の間、私たちの体は高温多湿の環境に適応するため、知らず知らずのうちに大きな負担を受けています。
・冷房による冷えと外気温の差:室内と屋外の温度差が大きいと、自律神経が体温調節に追われて疲弊します。
・乱れた生活リズム:夏は夜更かしや食生活の乱れが起こりやすく、体内リズムが崩れやすい時期です。
・季節の変化によるストレス:秋は朝晩の冷え込みや台風など気圧の変化が増え、これも自律神経に大きな影響を与えます。
こうした要因が重なると、倦怠感や食欲不振に加え、頭痛やめまいといった症状が現れることがあります。特に片頭痛やめまいで通院される方の中には、季節の変わり目に症状が強まるケースも少なくありません。
自律神経と頭痛・めまいの関係
自律神経は、体温や血流、消化などをコントロールしています。このバランスが乱れると、血管の収縮や拡張が不安定になり、頭痛を引き起こすことがあります。また、内耳の血流や神経機能にも影響が及ぶと、めまいやふらつきが出やすくなります。つまり、秋バテの根本には「自律神経の疲れ」があり、それが頭痛・めまいの悪化にも直結しているのです。
秋バテ対策のポイント

秋バテを防ぐには、自律神経を整える生活習慣が大切です。
1. 規則正しい生活:就寝・起床の時間を一定に保ち、朝は太陽の光を浴びることで体内時計をリセットしましょう。
2. 温度差に備える:薄手の上着を活用し、急な冷え込みに対応することが自律神経への負担軽減につながります。
3. 栄養バランスの良い食事:夏に消耗したビタミンやミネラルを意識的に補いましょう。特にビタミンB群やマグネシウムは神経の安定に役立ちます。
4. 軽い運動や入浴で血流改善:ウォーキングやストレッチなど無理のない運動、ぬるめのお風呂で体を温めることも効果的です。
まとめ
秋バテは「夏の疲れが抜けきらないまま迎える秋の不調」と言えます。特に頭痛やめまいが頻繁に起こる方は、自律神経の乱れが関与している可能性があります。日常生活の工夫で改善できる部分も多いですが、症状が続く場合は自己判断せず、医療機関にご相談ください。
ご不安なことがございましたら、お気軽に ながしま脳神経外科リハビリクリニック にご相談ください。