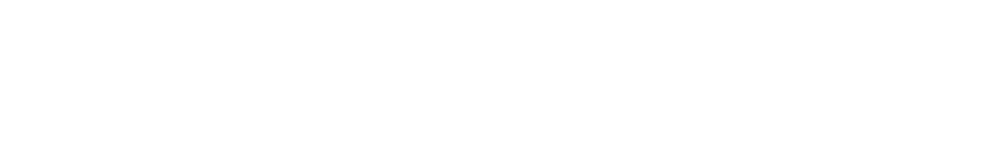前回は群発頭痛の特徴と原因、そして群発期と寛解期の違いについて解説しました。今回は、診断の流れや治療法、そして発作を防ぐために日常生活でできる工夫についてご紹介します。
群発頭痛の診断方法
群発頭痛の診断は、まず患者さんからの症状の聞き取り(問診)が中心になります。
特に注目するのは以下のようなパターンです。
• 片目の奥を中心に激しい痛みが繰り返される
• 発作の持続時間は15分〜3時間程度
• 群発期には1日に複数回発作が起こる
• 発作と同時に、涙・鼻水・まぶたの腫れ・顔の汗などの自律神経症状を伴う
こうした特徴がそろえば群発頭痛が強く疑われます。
ただし、発作性片側頭痛などの似た症状の病気もあります。これらは痛みの持続時間や頻度が少しずつ異なり、治療法も大きく違うため、正確な区別が必要です。
また、強い頭痛の裏に脳卒中や動脈瘤などの重い病気が隠れていることもあるため、MR検査や血液検査を行い、他の病気を除外することも診断の重要なステップです。
群発頭痛の治療方法
群発頭痛の治療は大きく分けて 「発作が起こったときに痛みを和らげる治療(急性期治療)」 と、
「群発期の発作を少しでも減らすための治療(予防治療)」 に分かれます。
急性期治療
激しい発作時には「トリプタン系薬剤」が効果的です。飲み薬のほか、発作が急速に進む場合は皮下注射や点鼻薬が使われることもあります。
また、酸素吸入療法も有効です。発作中に1分間に7リットル前後の酸素を15分ほど吸うことで、痛みが和らぐ方が少なくありません。診断が確定した患者さんには、自宅で酸素を吸入できる「在宅酸素療法(HOT)」が導入される場合もあります。
予防治療
群発期がある程度予測できる場合には、カルシウム拮抗薬(ベラパミルなど)が予防薬として使われます。これにより発作を軽くしたり、回数を減らしたりすることが期待できます。
在宅酸素療法を利用する際は、酸素は燃えやすいため取り扱いに注意が必要ですが、医師や業者の指導のもとで安全に使用することができます。

群発頭痛の予防と日常生活でできる工夫
群発頭痛は「群発期」と「寛解期」を繰り返す病気です。寛解期には症状が全くなく過ごせることが多いですが、次の群発期に備えて生活習慣を整えることが重要です。
アルコール・喫煙を避ける
特に群発期は、少量のアルコールでも必ず発作を誘発することがあります。そのため禁酒が必須です。喫煙も誘因になるため注意が必要です。
睡眠リズムを整える
睡眠不足や不規則な生活は体内時計を乱し、群発頭痛の引き金になります。毎日ほぼ同じ時間に寝起きする習慣を心がけましょう。
気圧の変化を避ける
飛行機搭乗や高山への旅行、スキューバダイビングなど、急な気圧変化は発作を悪化させることがあります。群発期はこうした行動を控えるのが安全です。
頭痛ダイアリーを活用する
「いつ」「どのくらいの痛みが」「どんな症状と一緒に」起きたかを記録しておくと、医師の診断や治療の精度が高まります。また、自分でも発作のパターンを把握でき、次の群発期に備えやすくなります。
まとめ
群発頭痛は、「目の奥がえぐられるような強い痛み」が群発期に集中して現れ、寛解期には嘘のように症状がなくなる病気です。その差の大きさが患者さんに大きな負担を与えますが、診断と治療を正しく受けることで症状をコントロールし、日常生活を取り戻すことができます。
ながしま脳神経外科リハビリクリニックでは、MR検査や血液検査などを組み合わせた総合的な診断を行い、患者さん一人ひとりの状況に合わせた治療を提案しています。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。