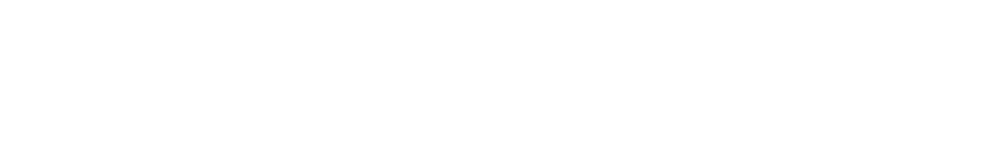近年、スマホの長時間使用による体への影響が注目されおり、そのひとつが「閃輝暗点(せんきあんてん)」という視覚異常です。視界にチカチカと光が見えたり、ギザギザした模様が現れたりと、スマホを見ていたときに急に違和感を覚える…そんな経験がある方もいるのではないでしょうか。
多くの場合、これは片頭痛の前ぶれとして起こる症状ですが、スマホの見過ぎが引き金となるケースや、頭痛を伴わない閃輝暗点も少なくありません。
「頭が痛くないから大丈夫」と思ってしまいがちですが、たとえ一時的に治まっても、スマホによる眼精疲労やストレスの蓄積が脳に影響を与えているサインかもしれません。放置せず、早めに医療機関を受診することが大切です。
この記事では、スマホと閃輝暗点の関係性やその原因、放置によるリスク、対処法、そして受診すべき診療科についてわかりやすくご紹介します。
当院では、スマホ使用による眼精疲労や頭痛、閃輝暗点に関するご相談にも対応しております。気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
頭痛がない閃輝暗点は危険?多くの方が放置しがちな「閃輝暗点」とは

閃輝暗点(せんきあんてん)とは、スマホ画面を見ている最中や直後に、視界にキラキラした光やギザギザとした模様が現れる現象のことです。はじめは視界の一部だけに見えるのが、次第に広がっていくのが特徴で、症状は数分から長くても数十分ほどで自然におさまることが多いとされています。
この現象は、片頭痛の前兆(予兆)としてよく知られていますが、実は頭痛がない場合にも起こることがあります。例えば、スマホの使い過ぎによる目や脳の疲労、低血糖や睡眠のとりすぎ、寝不足などの体調の変化がきっかけとなって発症するケースもあります。
一見すると「目の病気」のように思えますが、実際には脳内の血流に変化が起こることで発生する現象であり、目そのものに原因があるわけではありません。
閃輝暗点の原因とは?スマホの使い過ぎも一因に
閃輝暗点の主な原因は、脳の血管が一時的に収縮・拡張することです。これにはストレスや睡眠不足、食生活に加えて、スマホによる刺激の蓄積も関係していると考えられています。
ストレスが原因で起こる場合のメカニズム(スマホ使用が引き金に!?)
① ストレスがかかる(スマホ使用によるストレスや刺激も)
体内で「カテコールアミン」という物質が分泌される
(例:怒り・緊張・強い不安 など)
② 血小板が活性化
「セロトニン」という神経伝達物質が放出される
③ セロトニンの作用で
・脳の血管が一時的に収縮
・後頭部の「大脳皮質」の働きが一時的に低下
➡︎視界にキラキラ・ギザギザが見える(=閃輝暗点)
④ 神経細胞に変化が起きる
血管が今度は拡張+炎症が発生
⑤ 炎症が神経を刺激
三叉神経(さんさしんけい)が刺激される
➡︎ズキズキとした頭痛が起こる
※この流れは片頭痛にともなう閃輝暗点でよく見られるパターンです。すべての人に当てはまるわけではないため、気になる症状がある場合は医師にご相談ください。
閃輝暗点かな?と思ったら、何科を受診すればよい?

閃輝暗点が現れたときは、「頭痛があるかどうか」や「他にどんな症状があるか」によって、受診すべき診療科が変わります。スマホ使用後に視界に異常を感じたら、以下の症状に応じて診療科を選びましょう。
頭痛がない場合
閃輝暗点の症状が一時的で、日常生活に大きな支障がないようであれば、すぐに治療が必要とは限らない場合もあります。ただし、
・何度も繰り返す(スマホを使う度に起こる…)
・一度の症状が長く続く
・不安を感じる
といった場合には、まず「眼科」を受診して、目に異常がないかを確認してもらいましょう。
頭痛を伴う場合
スマホによる刺激が原因であっても、根本的な異常が隠れていることもあります。閃輝暗点とともに以下のような症状がある場合は、「脳神経外科」または「神経内科」を受診してみてください。
・ズキズキするような頭痛がある
・手足のしびれや力が入りにくい
・ものがうまく見えない・話しづらいなどの神経症状がある
閃輝暗点は、「目」ではなく脳の血流や神経に関連した異常が原因の可能性があります。しっかりと原因を調べて、必要に応じた治療を受けることが大切です。また、痛みが頭だけでなく、
・目の奥が痛む
・顔全体に違和感がある
といったケースもあります。「頭痛がないから大丈夫」と思わず、少しでも不安があれば専門医に相談することをおすすめします。
スマホ時代の閃輝暗点対処法とは?
①頭痛がある場合

頭痛をともなう閃輝暗点の場合は、まずは頭痛そのものの治療を優先することが大切です。市販薬ではなく、医師の診断のもと適切な治療を受けることで、閃輝暗点の頻度や強さの軽減にもつながります。スマホ使用時に症状が出る場合は使用時間や姿勢を見直すことも有効です。
②頭痛がない場合
一方で、頭痛のない閃輝暗点には、現時点でははっきりとした治療法が確立されていないのが現状です。以下の2つのポイントを意識することで、症状の予防や緩和が期待できることもあります。
◎医師が治療できないケースもある
MRIやCTなどの検査で異常が見つからず、日常生活に支障がないと判断された場合、医師からは「病気ではない」と診断され、治療の対象外(経過観察)となることもあります。これは、「医師法」や「薬機法(旧・薬事法)」に基づくもの で、病気と診断できない限り、薬などを使った治療が行えないためです。
ただし、症状が軽くても「不安を感じる」「気になる」というときは、スマホ使 用による慢性的な疲労が蓄積している場合もあるため、我慢せず定期的に相談することが大切です。経過をしっかり見守っていく姿勢も、安心につながります。
◎サプリメントを活用した栄養療法
近年では、「サプリメントによる栄養療法」が、閃輝暗点の予防や軽減に役立つ可能性があるとされています。これは、脳内のセロトニン不足を補ったり、炎症に関わる物質(プロスタグラン ジン)の働きを抑える目的で使われます。頭痛 のあるタイプ・ないタイプ、どちらの閃輝暗点にも有効とされているため、日常的な体調管理の一つとして取り入れてみるのも良いでしょう。
ただし、サプリメントは体質によって合う・合わないがあります。使用を始める 前には、必ず医師や専門家に相談することをおすすめします。
閃輝暗点の症状が軽い場合でも、「大丈夫だろう」と放置せず、まずは体のサインとして受け止めることが大切です。正しい対処を知ることで、日々の安心にもつながります。
まとめ

今回は、スマホ(携帯)の触り過ぎは閃輝暗点の原因に!?目がチカチカする原因を徹底解説という内容に基づいて解説してきましたが、いかがでしたか?
頭痛のない閃輝暗点は、一時的におさまることが多いため、つい放置してしまいがちですが、本来は起こるはずのない異常な視覚の変化であり、体の中で何かしらの変化が起きているサインかもしれません。
スマホは生活に欠かせない存在ですが、使い方次第で体に負担をかけることもあります。症状が軽くても、「一時的だから」と放置せず、早めに医師に相談することが大切です。
ながしま脳神経外科リハビリクリニックでは、必要な場合にはMRI検査や血液検査、心電図検査などを行い、脳の状態だけでなく全身の症状を確認し一人ひとりの症状やお悩みに合わせた頭痛治療を行っています。スマホの使い過ぎで体調に不安を感じる方、視界の異常や頭痛にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。