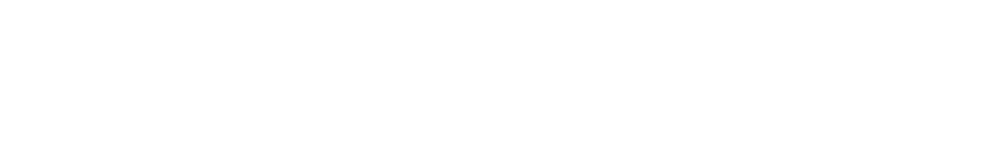更年期に差し掛かると、女性ホルモンバランスの変化が原因で頭痛が起こることがあります。
更年期の頭痛は、女性ホルモンの低下や自律神経の乱れ、過度なストレス、生活環境の変化などが影響しています。
特に、ストレスや過労、長時間同じ姿勢を取ること、眼精疲労や肉体疲労、睡眠不足、栄養素の不足(鉄分など)
さらには家族に片頭痛の人がいる場合などは、頭痛を引き起こしやすいことがあります。
ただし、適切な対策を取ることで症状を和らげることができるので、原因や対処法について理解しておくことが大切です。
この記事では、更年期の頭痛について悩んでいる方や、これから迎えることに不安を感じている方に向けて、原因や対処法をわかりやすく解説します。
また、痛みを軽減するための対処法や予防方法も紹介しますのでぜひ参考にしてください。
更年期に多い頭痛の種類
頭痛には、一次性頭痛と二次性頭痛の2つがあります。
一次性頭痛は、脳や神経、血管の機能異常が原因で起こるもので、「機能性頭痛」とも呼ばれます。一方、二次性頭痛は、別の病気や体の状態が引き金となる頭痛です。
更年期の頭痛の多くは一次性頭痛に分類されますが、強い痛みや症状が長引く場合には二次性頭痛の可能性もあるため、注意が必要です。
①一次性頭痛
一次性頭痛には、片頭痛、緊張型頭痛、薬剤誘発性頭痛などがあります。
片頭痛
片頭痛は、頭の片側または両側にズキズキとした脈を打つような痛みが特徴です。
痛みがひどくなると、吐き気を伴うこともあり、日常的な動作(例えば階段を昇るなど)によって痛みが悪化することが多いです。
片頭痛は、更年期による女性ホルモンバランスの変化が原因で起こることがあるので、頻繁に症状が現れる場合は、早めに医師に相談しましょう。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は、頭の両側や全体に圧迫感や締め付けられるような痛みを感じるのが特徴です。
主な原因としては、ストレスや姿勢の悪さ、運動不足などが挙げられ、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用も影響することがあります。女性ホルモンバランスの変化によって自律神経が乱れることも原因の一つで、のぼせることや火照り不眠などの症状を感じたら、適度なストレッチやリラックスを心がけましょう。
薬剤誘発性頭痛

薬剤誘発性頭痛は、鎮痛剤を過剰に使用することで引き起こされる頭痛です。頻繁に鎮痛剤を服用しているにもかかわらず、痛みが続く場合はこの種類の頭痛を疑うべきでしょう。
薬剤誘発性頭痛は、鎮痛剤の使用を減らすことで改善されることが多いので、薬を常用しているにもかかわらず痛みが治まらない場合は、医師に相談して適切な治療法を考える必要があります。
②二次性頭痛
二次性頭痛は、何らかの病気が原因で引き起こされる頭痛です。以下のような原因が考えられます。
● くも膜下出血
● 脳出血
● 脳梗塞
● 脳腫瘍
● 蓄膿症(副鼻腔炎) など
二次性頭痛は「急性頭痛」とも呼ばれ、脳や頭部に異常が生じることで発生します。突然、激しく頭が痛くなった場合や、強い痛みが長引く場合、徐々に痛みが強くなる場合は直ちに医療機関を受診しましょう。二次性頭痛の場合は、疾病によっては命に関わることもあります。
更年期に頭痛が起きる原因
更年期に頭痛が起こる原因として、卵胞ホルモンの減少、ストレスや精神的な負担、自律神経の乱れなどが挙げられます。
①卵胞ホルモン(エストロゲン)の減少
更年期に起こる片頭痛の主な原因は、卵胞ホルモン(エストロゲン)の減少です。エストロゲンは、妊娠や出産だけでなく、血管や筋肉、骨、さらには脳内の神経伝達物質のバランスを保つために重要な役割を果たしています。しかし、更年期に差し掛かると、女性ホルモンの分泌が減少し、さまざまな不調が現れやすくなります。
閉経後はエストロゲンの分泌が安定し、片頭痛の症状も次第に和らいでいくことが多いです。
②ストレス・精神的な負担
緊張型頭痛の原因の一つとして、ストレスや精神的な負担が挙げられます。更年期は女性ホルモンバランスの変化により、体調が不安定になりやすく、気分の浮き沈みが起こることがあり、このような精神的な負担が頭痛を引き起こしやすい原因となります。
③自律神経の乱れ

女性ホルモンの分泌をコントロールしている視床下部は、自律神経の調整にも深く関わっています。更年期やストレスが原因で視床下部の働きが乱れると、ホルモンバランスが崩れ、それが自律神経にも影響を与えます。
自律神経が乱れると、頭痛のほかにも、のぼせることや火照り不眠などの症状が現れることが増えます。
更年期に起きる頭痛への対処法
ここでは、日常生活の中でできる頭痛の対処法をご紹介します。
①ツボを押す
頭痛を和らげるために、首や肩の筋肉をほぐすことが有効です。また、ツボを刺激することも効果的だとされており頭痛に効果的なツボは以下の通りです。
● 百会(ひゃくえ):頭頂部で両耳と鼻の延長線が交わる場所
● 風池(ふうち):耳の後ろの骨と後頭部のくぼみの中間
● 天柱(てんちゅう):後頭部の髪の生え際
● 肩井(けんせい):首の付け根と両肩の端を結ぶ線の中央
● 印堂(いんどう):眉間の中央
● 太陽(たいよう):こめかみの内側
● 頷厭(がんえん):額の角の髪の生え際から少し下がったところ
手にもツボがあり、「前頭点」「頭頂点」「片頭点」「後頭点」などの頭に関連するツボを刺激することで、痛みの緩和が期待できます。
②漢方薬やサプリメントを摂る
食事だけで十分な栄養を摂取するのが難しい場合は、漢方薬やサプリメントを活用するのも一つの方法です。鉄分、ビタミンB2、マグネシウムなどを意識的に補うと良いでしょう。
更年期に入ると、エストロゲンの減少により、疲れや動悸(どうき)、めまいが現れやすくなります。鉄分が不足するとこれらの症状が悪化することもあるので、鉄分の摂取が大切です。
ビタミンB群は、冷え症や疲れ、肩こり、腰痛、めまい、生理痛、イライラ、無気力感などを改善する効果があります。マグネシウムにはリラックス効果があり、睡眠の質を向上させ、ストレス緩和にも役立ちます。
③市販の頭痛薬を服用する
痛みが強いときは、市販薬を使用するのも有効です。アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの成分が含まれる薬は痛みを和らげる効果があります。
ただし、薬の使用は短期的な対応として適しています。長期間の使用は副作用や依存のリスクが高まることがあるため、継続的に服用する場合は医師に相談しましょう。
④病院を受診する

頭痛がひどくなったり、頻繁に発生したりする場合は、早めに病院を受診しましょう。更年期の頭痛には、「当帰芍薬散」や「加味逍遥散」「桂枝茯苓丸」などを処方されることがあります。
激しい痛みが続く、痛みの強さや頻度が増している、または痛みに加えて神経症状(しびれや麻痺)が現れている場合は、何らかの病気が原因となっていることも考えられるため速やかに医師の診察を受けましょう。
更年期の頭痛を和らげる生活習慣のコツ
更年期の頭痛を軽減するためには、生活習慣を見直すことが重要です。
①適度な運動
軽い運動を取り入れることで、血行が促進され、頭痛の軽減が期待できます。ストレッチやヨガ、ウォーキングなどは、体に負担をかけずに続けやすいのでおすすめです。
運動はストレスの解消にも効果があります。ストレスが頭痛を悪化させる原因となるため、日常的に体を動かすことが大切です。
②栄養バランスの整った食事
食事の内容を見直すことで、頭痛の予防に繋がります。特に、タンパク質や鉄分をしっかり摂取するよう心がけましょう。また、コーヒーや紅茶などのカフェインは過剰に摂取すると頭痛を引き起こすことがあるため、カフェインの摂取量を控えめにし、ハーブティーやノンカフェインの飲み物を取り入れると良いでしょう。
③こまめな水分補給

更年期には、ホットフラッシュや寝汗で脱水症状が起こりやすくなります。水分不足は血行不良を引き起こし、頭痛の原因となるため、十分な水分補給を心がけましょう。
朝起きたときや運動後などは特に水分が不足しやすいので、こまめに補給することが大切です。
外的刺激も頭痛の原因となることがあるため、外出先では直射日光や寒暖差、乾燥、湿気、騒音などの環境に注意しましょう。
まとめ
今回は更年期の頭痛の原因や対処法について解説しました。
更年期に伴う頭痛は、女性ホルモンの変化やストレス、自律神経の乱れなどが原因で発生することが多く、のぼせることや火照り、不眠などの症状が特徴的です。
片頭痛や緊張型頭痛は特に注意が必要で、突然の激しい痛みや神経症状を伴う場合は、二次性頭痛の可能性があるため、早期の受診が重要になります。日常生活でできる対処法としては、軽い運動やストレッチ、食事の見直し、水分補給が効果的です。
また、ツボ押しや漢方薬、サプリメントの活用も有効ですが、頭痛が頻繁に発生したり悪化したりする場合は、病院での適切な診断と治療を受けましょう。
ながしま脳神経外科リハビリクリニックでは、必要な場合にはMRI検査や血液検査、心電図検査などを行い、脳の状態だけでなく全身の症状を確認し一人ひとりの症状やお悩みに合わせた頭痛治療を行っています。また漢方薬専門医による外来診療も行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。